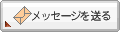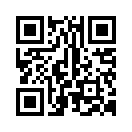2018年01月15日
緑藻の観察
泡瀬干潟では昨年の3月と5月頃に緑藻の仲間が大発生しました。
今年も発生するのかどうか観察しようと思い泡瀬干潟に行きました。
この日の干潮はそれほど潮が引かず、干潟の大部分は水の中でした。
今日は干出している部分をゆっくり観察することにしました。
沖合では人工島の工事が続いています。


浜に降りて潮が運んできた漂着物を見てみます。
ホンダワラの仲間の藻類に混じってそら豆のような種子を見つけました。
取り上げてよく見てみると海草の種子によく似ていました。

干潟に降りて歩いていくと、イソスギナなどの藻類が繁殖している潮溜まりが
ありました。緑、黄緑、茶、うす茶、赤っぽいものなどカラフルです。
まるで海の中の熱帯雨林のようです。



そこから沖に向い、波打ち際を回るように観察しました。
ところどころに昨年の春に大発生した緑藻に似た藻類がありました。
まだそれほど拡がってはいないようですが、集まっている部分もありました。


ピンセットを使い、藻の表面を持ち上げてみると、布のような感じです。
その一部を切り取り、マクロレンズを装着した一眼レフで撮影してみました。
藻の状態がわかるように太陽に透かして撮影しました。
画像を見ると肉眼でははっきりと見えない藻の状態が写っていました。
かなり密に絡んでいます。このような藻類に覆い被されたらその下に
生息する生きものは窒息しそうです。




最干の時刻が過ぎてしばらくすると上げ潮が始まりました。
平らな干潟にあちこちから潮がどんどん押し寄せてきます。
潮に追われるように陸に向かいながら生きものを観察しました。
岩礁のくぼみにカニがいました。体の割にハサミが大きく
強そうです。

小さなスナジャワンがありました。タマガイの仲間の卵塊です。
砂を利用して作るそうですが、表面はつるっとしていて芸術品のようです。
どのようにして作るのでしょうか。不思議です。


朽ちた二枚貝を見つけました。穴が開いています。
貝の成分は徐々に海水に溶けていき、再び何かの殻などの材料となるのでしょう。

少し高くなった岩礁で昔のサンゴを観察しました。

先日見に行った県立博物館・美術館で開催していた「海の沖縄」という展示で
沖縄県の地質や岩石について様々な解説がありました。
その中に現在のサンゴ礁は、最終の間氷期が終わった後、海水面が上昇し、
約9500年前から成長が始まったという解説がありました。
この泡瀬に残る岩となったサンゴは、いつ頃生きていたのでしょうか?
その時の海面は今より高かったはずですが、この辺りはどのような環境だったの
でしょうか?




泡瀬干潟の成り立ちに興味が湧いてきます。
干潟の地層深くには、過去に生きていた生きものたちの痕跡が堆積しているの
でしょうか?そのようなことを考えながら観察しました。
陸へ戻る時、釣り糸を見つけました。鳥の足に絡まったら大変です、回収する
ことにしました。

波打ち際には鳥たちが集まってきて、賑やかに食事をはじめました。
彼らの大切なひとときをじゃまをしないように、干潟から立ち去りました。
今年も発生するのかどうか観察しようと思い泡瀬干潟に行きました。
この日の干潮はそれほど潮が引かず、干潟の大部分は水の中でした。
今日は干出している部分をゆっくり観察することにしました。
沖合では人工島の工事が続いています。


浜に降りて潮が運んできた漂着物を見てみます。
ホンダワラの仲間の藻類に混じってそら豆のような種子を見つけました。
取り上げてよく見てみると海草の種子によく似ていました。

干潟に降りて歩いていくと、イソスギナなどの藻類が繁殖している潮溜まりが
ありました。緑、黄緑、茶、うす茶、赤っぽいものなどカラフルです。
まるで海の中の熱帯雨林のようです。



そこから沖に向い、波打ち際を回るように観察しました。
ところどころに昨年の春に大発生した緑藻に似た藻類がありました。
まだそれほど拡がってはいないようですが、集まっている部分もありました。


ピンセットを使い、藻の表面を持ち上げてみると、布のような感じです。
その一部を切り取り、マクロレンズを装着した一眼レフで撮影してみました。
藻の状態がわかるように太陽に透かして撮影しました。
画像を見ると肉眼でははっきりと見えない藻の状態が写っていました。
かなり密に絡んでいます。このような藻類に覆い被されたらその下に
生息する生きものは窒息しそうです。




最干の時刻が過ぎてしばらくすると上げ潮が始まりました。
平らな干潟にあちこちから潮がどんどん押し寄せてきます。
潮に追われるように陸に向かいながら生きものを観察しました。
岩礁のくぼみにカニがいました。体の割にハサミが大きく
強そうです。

小さなスナジャワンがありました。タマガイの仲間の卵塊です。
砂を利用して作るそうですが、表面はつるっとしていて芸術品のようです。
どのようにして作るのでしょうか。不思議です。


朽ちた二枚貝を見つけました。穴が開いています。
貝の成分は徐々に海水に溶けていき、再び何かの殻などの材料となるのでしょう。

少し高くなった岩礁で昔のサンゴを観察しました。

先日見に行った県立博物館・美術館で開催していた「海の沖縄」という展示で
沖縄県の地質や岩石について様々な解説がありました。
その中に現在のサンゴ礁は、最終の間氷期が終わった後、海水面が上昇し、
約9500年前から成長が始まったという解説がありました。
この泡瀬に残る岩となったサンゴは、いつ頃生きていたのでしょうか?
その時の海面は今より高かったはずですが、この辺りはどのような環境だったの
でしょうか?




泡瀬干潟の成り立ちに興味が湧いてきます。
干潟の地層深くには、過去に生きていた生きものたちの痕跡が堆積しているの
でしょうか?そのようなことを考えながら観察しました。
陸へ戻る時、釣り糸を見つけました。鳥の足に絡まったら大変です、回収する
ことにしました。

波打ち際には鳥たちが集まってきて、賑やかに食事をはじめました。
彼らの大切なひとときをじゃまをしないように、干潟から立ち去りました。
Posted by 有光智彦 at 23:26
│海の生きもの 1~3月│海 泡瀬干潟