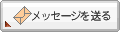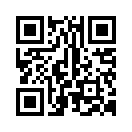2009年06月17日
泡瀬の現在
6月6日に泡瀬の海に入りました。
調査に同行させてもらいました。
前回ブログにアップしたのは3月でした。
その頃は,カゴメノリという海藻が繁殖する時期にあたり,調査を
継続している「ヒメマツミドリイシ」群落もすっかりとこの海藻に
包まれていました。
今回は,この海藻も姿を消し,サンゴ礁の現状があらわになりました。
これから書く記事は私の主観に基づくものですが,写真は,現実を
映し出しています。
泡瀬干潟の埋め立て工事が始まる前のサンゴ礁は,非常に元気で
生き生きとしていたと聴いています。
私は残念ながら当時のすばらしい海中を見ていません。
僅かに数年前の工事が始まる前の海中を知る者は,
今の現状を目の当たりにして,手足が震えるほど落胆することでしょう。
1998年の世界的なサンゴ礁の白化現象にも耐えて存続し続けていた
貴重なサンゴ礁だったのです。
何千年という長い時をかけて形成されてきたであろう泡瀬のサンゴ礁を
人間はたった数年で破壊しました。
長い長い自然の歴史の歩みを止めてしまったのです。
調査日の天候は晴れ,穏やかな一日でした。
調査地点は,前回同様に「ヒメマツミドリイシ」の群落と
移植サンゴの状況確認です。
「ヒメマツミドリイシ」の群落近くにアンカーを入れますが,海底にサンゴが無いか,
生きものが居ないかを確かめてからです。
適当な岩礁にしっかりとアンカーを咬ませます。
そうしていると,さっそく「トラギス」君が見物にやって来ました。
好奇心のとても強い魚です。

「ヒメマツミドリイシ」の群落は,死滅した部分が広大に広がっていました。
生きている部分が少ないように見えます。
もし,ここで工事を中止するならば,おそらくこのサンゴ礁は回復するでしょう。
いままで幾多の自然現象から何千年と生き抜いてきた生命力を持っているからです。


まだ可能性は十分残っています。
時間がかかるでしょうが,回復は可能です。
自然は,力強い。
前回同様に海中には,砂塵が舞い視界はほんの数メートルしかありません。
毎回見かけるスズメダイの群れも見られません。
僅かに残った元気なサンゴに集まるように「ミヤコイシモチ」の群れが泳いで
いました。
この魚も,他の魚同様にこちらを正面から見るしぐさをします。
私は,横向きの写真を撮りたいのになかなか撮らせてもらえません。
「こら!あっちを向きなさい。」と言ったところで言うことをきくはずもありません。


濁った海底を這うように生きものを探します。
次に出逢ったのは「クチナガイシヨウジ」です。
海藻の上を移動していました。

死滅したサンゴには生きものは居ません。
痛々しい残骸がそこにあるだけです。
時間とともに崩れ去り,沖縄のどこのイノーでも見られるようなサンゴ礁の
がれきの山が残るだけでしょう。

私たちは,ボートに乗り込み次の調査地点に向かいます。
次は,埋め立て区域から移植したとされるサンゴのポイントです。
沖の防波堤の内側で港内の一角です。
あいかわらず濁りがひどく,わずか2メートル下が見えません。
海中は,砂塵が舞っていました。
初めての人なら,この海を泳ぐのは不気味で泳げないでしょう。
こんな晴天の日でも海底にとどく光はわずかです。
それに今は干潮にあたっていました。
サンゴにとって太陽の光は最も大切なエネルギー源です。
その光が届かないのは致命的でしょう。
前回とサンゴの様子は変わっていないようにも見えます。
死滅した部分はそのままです。

新たにサンゴを追加した痕跡がありました。
とても元気なサンゴばかりを一カ所に集めています。
その上にサンゴの卵を受け取る装置が取り付けてありました。
ちょうど今がサンゴの産卵のシーズンです。
いったいどのような目的で移植したサンゴの卵を採取しようとしているのでしょうか。

急激に悪くなっていくサンゴ礁の状態を見て,参加した各自は胸が痛んだと思います。
そして私の目にも生きものが少なくなっている現状が読みとれました。
次回の調査の時,どうなっているかが今から心配です。

調査に同行させてもらいました。
前回ブログにアップしたのは3月でした。
その頃は,カゴメノリという海藻が繁殖する時期にあたり,調査を
継続している「ヒメマツミドリイシ」群落もすっかりとこの海藻に
包まれていました。
今回は,この海藻も姿を消し,サンゴ礁の現状があらわになりました。
これから書く記事は私の主観に基づくものですが,写真は,現実を
映し出しています。
泡瀬干潟の埋め立て工事が始まる前のサンゴ礁は,非常に元気で
生き生きとしていたと聴いています。
私は残念ながら当時のすばらしい海中を見ていません。
僅かに数年前の工事が始まる前の海中を知る者は,
今の現状を目の当たりにして,手足が震えるほど落胆することでしょう。
1998年の世界的なサンゴ礁の白化現象にも耐えて存続し続けていた
貴重なサンゴ礁だったのです。
何千年という長い時をかけて形成されてきたであろう泡瀬のサンゴ礁を
人間はたった数年で破壊しました。
長い長い自然の歴史の歩みを止めてしまったのです。
調査日の天候は晴れ,穏やかな一日でした。
調査地点は,前回同様に「ヒメマツミドリイシ」の群落と
移植サンゴの状況確認です。
「ヒメマツミドリイシ」の群落近くにアンカーを入れますが,海底にサンゴが無いか,
生きものが居ないかを確かめてからです。
適当な岩礁にしっかりとアンカーを咬ませます。
そうしていると,さっそく「トラギス」君が見物にやって来ました。
好奇心のとても強い魚です。

「ヒメマツミドリイシ」の群落は,死滅した部分が広大に広がっていました。
生きている部分が少ないように見えます。
もし,ここで工事を中止するならば,おそらくこのサンゴ礁は回復するでしょう。
いままで幾多の自然現象から何千年と生き抜いてきた生命力を持っているからです。


まだ可能性は十分残っています。
時間がかかるでしょうが,回復は可能です。
自然は,力強い。
前回同様に海中には,砂塵が舞い視界はほんの数メートルしかありません。
毎回見かけるスズメダイの群れも見られません。
僅かに残った元気なサンゴに集まるように「ミヤコイシモチ」の群れが泳いで
いました。
この魚も,他の魚同様にこちらを正面から見るしぐさをします。
私は,横向きの写真を撮りたいのになかなか撮らせてもらえません。
「こら!あっちを向きなさい。」と言ったところで言うことをきくはずもありません。
濁った海底を這うように生きものを探します。
次に出逢ったのは「クチナガイシヨウジ」です。
海藻の上を移動していました。

死滅したサンゴには生きものは居ません。
痛々しい残骸がそこにあるだけです。
時間とともに崩れ去り,沖縄のどこのイノーでも見られるようなサンゴ礁の
がれきの山が残るだけでしょう。

私たちは,ボートに乗り込み次の調査地点に向かいます。
次は,埋め立て区域から移植したとされるサンゴのポイントです。
沖の防波堤の内側で港内の一角です。
あいかわらず濁りがひどく,わずか2メートル下が見えません。
海中は,砂塵が舞っていました。
初めての人なら,この海を泳ぐのは不気味で泳げないでしょう。
こんな晴天の日でも海底にとどく光はわずかです。
それに今は干潮にあたっていました。
サンゴにとって太陽の光は最も大切なエネルギー源です。
その光が届かないのは致命的でしょう。
前回とサンゴの様子は変わっていないようにも見えます。
死滅した部分はそのままです。
新たにサンゴを追加した痕跡がありました。
とても元気なサンゴばかりを一カ所に集めています。
その上にサンゴの卵を受け取る装置が取り付けてありました。
ちょうど今がサンゴの産卵のシーズンです。
いったいどのような目的で移植したサンゴの卵を採取しようとしているのでしょうか。
急激に悪くなっていくサンゴ礁の状態を見て,参加した各自は胸が痛んだと思います。
そして私の目にも生きものが少なくなっている現状が読みとれました。
次回の調査の時,どうなっているかが今から心配です。

Posted by 有光智彦 at 02:36
│海 泡瀬干潟
この記事へのコメント
小橋川共男さんの『こんにちは泡瀬干潟』をご存知でしょうか?
生き生きとしたさんご礁や干潟の生き物たちの変貌に私はただただ驚かされています。
有光さんの珊瑚礁などの海中のドキュメンタリーさすがですね。
ぜひぜひ時間作ってご教授してくださいね。
生き生きとしたさんご礁や干潟の生き物たちの変貌に私はただただ驚かされています。
有光さんの珊瑚礁などの海中のドキュメンタリーさすがですね。
ぜひぜひ時間作ってご教授してくださいね。
Posted by 豊里 at 2009年06月21日 14:34
豊里 様
写真活動は順調ですか。
小橋川さんの写真集を数冊購入し自然の大好きな方々に
プレゼントしました。あの写真集ができるまで,何年も掛かかったこと
でしょう。長く一つのテーマを追う姿勢を見習いたいと思います。
写真活動は順調ですか。
小橋川さんの写真集を数冊購入し自然の大好きな方々に
プレゼントしました。あの写真集ができるまで,何年も掛かかったこと
でしょう。長く一つのテーマを追う姿勢を見習いたいと思います。
Posted by 有光智彦 at 2009年06月27日 13:07
at 2009年06月27日 13:07
 at 2009年06月27日 13:07
at 2009年06月27日 13:07