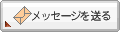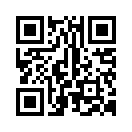2011年02月28日
シンポジュウム
3月5日サンゴの日に、沖縄県名護市で、シンポジウム
「大浦湾のアオサンゴをよく知り、名護の海の将来を考えてみよう」を行
います。多くの方のご参加をお待ちしています。
2007年9月に大浦湾チリビシのアオサンゴ群集が発見されました。その
後、大規模な白化現象などさまざまなことがありました。それらを振り返
ってまとめてご紹介します。
沖縄の人は昔からサンゴ礁の海と上手に付き合ってきました。しかしな
がら最近は悲しい光景を見ることが多いという声が聞こえてくるようにな
りました。
新市長を迎え、名護市は新たな可能性を模索しはじめています。ここで改
めて人と海のつきあい方はどうあるべきか、どうしていくのが良いのか、
3月5日のサンゴの日に一緒に考えてみませんか。
日 時: 3月5日(土) 13:30〜16:30 (開場13時)
場 所: 大西公民館 (沖縄県名護市大西3丁目8-12)
参加費: 無料
主 催: 日本自然保護協会
共 催: 北限のジュゴンを見守る会チームザン、沖縄生物多様性市民ネ
ットワーク、 名護の自然を守り次世代に伝えたい市民の会
【プログラム】
1. 『大浦湾チリビシのアオサンゴ群集 〜発見から白化回復まで 〜』
安部真理子(日本自然保護協会)
2. 『アオサンゴの科学・サンゴ礁の科学』
中野義勝(琉球大学瀬底実験所)
3. パネルディスカッション 名護の海の将来を考える
事例報告
『沖縄島各地の海を見て』 有光智彦(水中写真家)
『名護市東江の事例を通じて』吉元宏樹 (名護の自然を守り次世
代に伝えたい市民の会)
パネリスト:有光智彦、吉元宏樹、中野義勝、キャサリン・ミュージック
(理学博士・海洋学者)、安部真理子
問い合わせ:日本自然保護協会 保護プロジェクト部 安部真理子
(〜3/3までtel:03-3553-4103, 3/4以降はtel:080-5067-0957)
e-mail: abe@nacsj.or.jp
「大浦湾のアオサンゴをよく知り、名護の海の将来を考えてみよう」を行
います。多くの方のご参加をお待ちしています。
2007年9月に大浦湾チリビシのアオサンゴ群集が発見されました。その
後、大規模な白化現象などさまざまなことがありました。それらを振り返
ってまとめてご紹介します。
沖縄の人は昔からサンゴ礁の海と上手に付き合ってきました。しかしな
がら最近は悲しい光景を見ることが多いという声が聞こえてくるようにな
りました。
新市長を迎え、名護市は新たな可能性を模索しはじめています。ここで改
めて人と海のつきあい方はどうあるべきか、どうしていくのが良いのか、
3月5日のサンゴの日に一緒に考えてみませんか。
日 時: 3月5日(土) 13:30〜16:30 (開場13時)
場 所: 大西公民館 (沖縄県名護市大西3丁目8-12)
参加費: 無料
主 催: 日本自然保護協会
共 催: 北限のジュゴンを見守る会チームザン、沖縄生物多様性市民ネ
ットワーク、 名護の自然を守り次世代に伝えたい市民の会
【プログラム】
1. 『大浦湾チリビシのアオサンゴ群集 〜発見から白化回復まで 〜』
安部真理子(日本自然保護協会)
2. 『アオサンゴの科学・サンゴ礁の科学』
中野義勝(琉球大学瀬底実験所)
3. パネルディスカッション 名護の海の将来を考える
事例報告
『沖縄島各地の海を見て』 有光智彦(水中写真家)
『名護市東江の事例を通じて』吉元宏樹 (名護の自然を守り次世
代に伝えたい市民の会)
パネリスト:有光智彦、吉元宏樹、中野義勝、キャサリン・ミュージック
(理学博士・海洋学者)、安部真理子
問い合わせ:日本自然保護協会 保護プロジェクト部 安部真理子
(〜3/3までtel:03-3553-4103, 3/4以降はtel:080-5067-0957)
e-mail: abe@nacsj.or.jp
Posted by 有光智彦 at 15:29
│名護市東江 人工海浜
この記事へのコメント
このようなシンポジウムが開かれるのは、とっても良いことだと思います。
わたしも生き物が大好きです。
でも人間の安全とどちらが大切か?と問われれば、答える事はできません。
・・・しかし、多様な生き物が住めなくなる環境とは、果たして人間にとって本当に安全で暮らしやすいものなのか?違う気がします。
人間のくらしは大切です。
でも、たくさんの生き物たちと持ちつ持たれつで、安全に暮らせる方法はきっとあるのではないでしょか?
わたしも生き物が大好きです。
でも人間の安全とどちらが大切か?と問われれば、答える事はできません。
・・・しかし、多様な生き物が住めなくなる環境とは、果たして人間にとって本当に安全で暮らしやすいものなのか?違う気がします。
人間のくらしは大切です。
でも、たくさんの生き物たちと持ちつ持たれつで、安全に暮らせる方法はきっとあるのではないでしょか?
Posted by くぼた at 2011年02月28日 22:46
くぼた 様
こんばんは。
私も日々悩み続けています。
しかし,一つの可能性を信じています。
それは,知るということです。
海でも山でも川でも,どこにでもある野原でも
無数の生きものたちが人間の活動など無関係に
日々の営みを続けています。
その一匹一匹の命の実存を知ることが
大切だと思うのです。
それを知った時から人間として,または人間社会が
どのように自然界と接していったらよいのか
自ずと答えが出ると思うのです。
例えば,戦争でも,相手の国の小さな町で,幼子と両親が
お風呂に入り,食卓を並べて団らんをしていると知ったら
核弾頭の発射ボタンを誰が押すことができるでしょうか。
これと同じように海の中の生きものたちの実存を知ることで,
むやみに痛めつけたりはできないだろうと思うのです。
コメント,ありがとうございます。
こんばんは。
私も日々悩み続けています。
しかし,一つの可能性を信じています。
それは,知るということです。
海でも山でも川でも,どこにでもある野原でも
無数の生きものたちが人間の活動など無関係に
日々の営みを続けています。
その一匹一匹の命の実存を知ることが
大切だと思うのです。
それを知った時から人間として,または人間社会が
どのように自然界と接していったらよいのか
自ずと答えが出ると思うのです。
例えば,戦争でも,相手の国の小さな町で,幼子と両親が
お風呂に入り,食卓を並べて団らんをしていると知ったら
核弾頭の発射ボタンを誰が押すことができるでしょうか。
これと同じように海の中の生きものたちの実存を知ることで,
むやみに痛めつけたりはできないだろうと思うのです。
コメント,ありがとうございます。
Posted by 有光智彦 at 2011年03月01日 01:56
at 2011年03月01日 01:56
 at 2011年03月01日 01:56
at 2011年03月01日 01:56