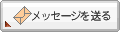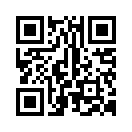2011年04月19日
エコ・コースト
海岸整備の方法に国土交通省が定めたエコ・コーストという事業がある。
国土交通省のホームページには,周辺の自然環境に配慮した自然と共生する
海岸の創出ということが書かれている。
(エコ・コーストで検索すると最初に表示される)
この発想で沖縄の護岸工事が進められてきた。
これからも続けられる予定。
この事業では人工リーフを設置し魚礁や藻場を造るとも書かれている。
額面では自然と共生すると書かれてはいるが実際はどうだろうか。
東江の護岸工事では,沖合に幅約50メートル長さ約600メートルの
面積にコンクリートブロックを並べている。

この人工リーフには,高波のエネルギーを打ち消す役目で設置されたが,
工事区域内のサンゴの移植場所にもなっている。しかし,サンゴの生存率は
悪いことがわかる(北部土木事務所が現場に看板を設置)。
もともとこの場所は砂地と岩礁があったことが過去の航空写真から
わかっている。残された海底に海草(ウミヒルモなど)藻場を確認している
ことから,そのような海底にコンクリートブロックを設置したものと
推定できる。
陸地から見た人工リーフは大潮の干潮の時以外は水面下に
あり,見ることができない。これだけのものを浅い海の中に沈め,
もともとある生態系を破壊することがどうして自然と共生することに
なるのだろうか。
このエコ・コースト事業により既に完成している海岸がある。
沖縄本島の中城湾に面した吉の浦公園に面している海岸がそれである。

過去この海岸がどのような場所であったかの手がかりが一枚の写真に
克明に残っている。昭和50年代に空撮されたその写真には砂浜があり
遠浅の海が写っている。

いったい何故わざわざそのような場所を造成する必要があったので
あろうか。そのままではいけなかったのか。
この浜は白砂である。よく見ると人工海浜に用いられる海砂に似ている。
このような人工の砂浜には生きものはほとんど住んでいないのが現状である。

沖縄近海から採取される海砂はサンゴ礁由来のものなので白色であり,
これを浜に使うと海の色が美しい空色になるのが特徴である。
だから人工海浜を造ることが好まれる理由の一つでもありそうだ。
しかし,もともと無いものを持ってきて,自然の砂浜の上に覆いかぶせる
ことこそが自然破壊ではなかろうか。
また,突堤や護岸に自然石を用いることが多いようだ。
自然にみせかけているつもりだろうが,私にはよっぽど不自然に見える。
センスがよほど悪い。誰が決めたのであろうか。
これなら見慣れたコンクリートの方がましだ。

吉の浦公園の北側の防波堤を越えると昔ながらの浜が延々と続いていた。
ゴミこそ多いが自然の浜である。ここなら生きものが住んでいるはずだ。
砂の色はグレーでおそらく岩石由来である。
サンゴや貝殻のかけらがたくさん落ちている。

こんな具合に沖縄の海岸が変えられていこうとしている。
沖縄だけでなく全国のみなさんの海岸もターゲットになっていることを
知らなければなりません。
気が付いたときには工事が終わっているということになりかねない。
幼少の頃から親しんできた自然の海岸がことごとく変貌していく。
もし,それがいやならいち早く事業の計画を察知し,内容を精査して異議が
あるなら,勇気を持って意見を伝えていかねばなるまい。
エコ・コースト事業は,市民が慎重にモニターする必要がありそうだ。
このままでは,エコ・コーストではなく,エゴ・コーストになってしまう。
国が行う事業は正しいという保証は絶対に無いと思う。
問題意識を持ち,自分の目で確かめると,その内容に矛盾があることが
わかってくる。
行政の発する言葉はいつも美しい内容だが,事実と異なっている。

原発の絶対安全神話は脆くも崩れ去った。
原発の危険性を説いて全国を廻っていた人や書籍もたくさん出版されていたにも
関わらずこんな結果となってしまった。
私自身にも言えることだが,みんなが関心を持っていれば変えられたかも
しれない。
そのことが全国の海岸の変貌についても言えると思うのです。
一人一人が,日常の生活の中で,常にこれでよいのかという疑問を持つ習慣を
つければ,何事にも無関心に陥ることは少なくなると思う。
日本国民は,昔から,ながいものにはまかれろ的思考が多いように思う。
かつて私もそうであったように。
小学校の頃から何か失敗をすると全体責任とし足並みをそろえさせたり,
自己主張をひかえさせた教育に原因の一端があるように思えてならない。
日本が住みよい社会になるためには,一人一人が社会の問題点に関心を持ち,
真剣に考え,正しいと思うことを行動で示すことが大切ではなかろうか。
みなさんはどう思われますか。

国土交通省のホームページには,周辺の自然環境に配慮した自然と共生する
海岸の創出ということが書かれている。
(エコ・コーストで検索すると最初に表示される)
この発想で沖縄の護岸工事が進められてきた。
これからも続けられる予定。
この事業では人工リーフを設置し魚礁や藻場を造るとも書かれている。
額面では自然と共生すると書かれてはいるが実際はどうだろうか。
東江の護岸工事では,沖合に幅約50メートル長さ約600メートルの
面積にコンクリートブロックを並べている。

この人工リーフには,高波のエネルギーを打ち消す役目で設置されたが,
工事区域内のサンゴの移植場所にもなっている。しかし,サンゴの生存率は
悪いことがわかる(北部土木事務所が現場に看板を設置)。
もともとこの場所は砂地と岩礁があったことが過去の航空写真から
わかっている。残された海底に海草(ウミヒルモなど)藻場を確認している
ことから,そのような海底にコンクリートブロックを設置したものと
推定できる。
陸地から見た人工リーフは大潮の干潮の時以外は水面下に
あり,見ることができない。これだけのものを浅い海の中に沈め,
もともとある生態系を破壊することがどうして自然と共生することに
なるのだろうか。
このエコ・コースト事業により既に完成している海岸がある。
沖縄本島の中城湾に面した吉の浦公園に面している海岸がそれである。

過去この海岸がどのような場所であったかの手がかりが一枚の写真に
克明に残っている。昭和50年代に空撮されたその写真には砂浜があり
遠浅の海が写っている。

いったい何故わざわざそのような場所を造成する必要があったので
あろうか。そのままではいけなかったのか。
この浜は白砂である。よく見ると人工海浜に用いられる海砂に似ている。
このような人工の砂浜には生きものはほとんど住んでいないのが現状である。

沖縄近海から採取される海砂はサンゴ礁由来のものなので白色であり,
これを浜に使うと海の色が美しい空色になるのが特徴である。
だから人工海浜を造ることが好まれる理由の一つでもありそうだ。
しかし,もともと無いものを持ってきて,自然の砂浜の上に覆いかぶせる
ことこそが自然破壊ではなかろうか。
また,突堤や護岸に自然石を用いることが多いようだ。
自然にみせかけているつもりだろうが,私にはよっぽど不自然に見える。
センスがよほど悪い。誰が決めたのであろうか。
これなら見慣れたコンクリートの方がましだ。

吉の浦公園の北側の防波堤を越えると昔ながらの浜が延々と続いていた。
ゴミこそ多いが自然の浜である。ここなら生きものが住んでいるはずだ。
砂の色はグレーでおそらく岩石由来である。
サンゴや貝殻のかけらがたくさん落ちている。

こんな具合に沖縄の海岸が変えられていこうとしている。
沖縄だけでなく全国のみなさんの海岸もターゲットになっていることを
知らなければなりません。
気が付いたときには工事が終わっているということになりかねない。
幼少の頃から親しんできた自然の海岸がことごとく変貌していく。
もし,それがいやならいち早く事業の計画を察知し,内容を精査して異議が
あるなら,勇気を持って意見を伝えていかねばなるまい。
エコ・コースト事業は,市民が慎重にモニターする必要がありそうだ。
このままでは,エコ・コーストではなく,エゴ・コーストになってしまう。
国が行う事業は正しいという保証は絶対に無いと思う。
問題意識を持ち,自分の目で確かめると,その内容に矛盾があることが
わかってくる。
行政の発する言葉はいつも美しい内容だが,事実と異なっている。

原発の絶対安全神話は脆くも崩れ去った。
原発の危険性を説いて全国を廻っていた人や書籍もたくさん出版されていたにも
関わらずこんな結果となってしまった。
私自身にも言えることだが,みんなが関心を持っていれば変えられたかも
しれない。
そのことが全国の海岸の変貌についても言えると思うのです。
一人一人が,日常の生活の中で,常にこれでよいのかという疑問を持つ習慣を
つければ,何事にも無関心に陥ることは少なくなると思う。
日本国民は,昔から,ながいものにはまかれろ的思考が多いように思う。
かつて私もそうであったように。
小学校の頃から何か失敗をすると全体責任とし足並みをそろえさせたり,
自己主張をひかえさせた教育に原因の一端があるように思えてならない。
日本が住みよい社会になるためには,一人一人が社会の問題点に関心を持ち,
真剣に考え,正しいと思うことを行動で示すことが大切ではなかろうか。
みなさんはどう思われますか。

Posted by 有光智彦 at 02:19
│名護市東江 人工海浜
この記事へのコメント
有光さん
わかりやすいご説明ありがとうございます。
今日、知人が東江の海を見に来てくれたのですが、
人工リーフを見て「魚のすみかを作ってるんでしょ?」と言いました。
護岸工事や養浜が今までの自然を変えてしまうのはわかるけど、また新しい自然が生まれないとも限らないでしょう、と。
60代のヤンバル生まれ育ちの方で自然を愛する気持ちも持っている方なのですが。
私は知識がなくて答えられませんでした。
この記事を紹介しようと思います。
今日は晴天で、東江の人工ビーチでシュノーケリングを楽しむ若者たちが居ました。
けっこう波が荒かったですが、人工リーフの上まで行っていました。
彼らが自然の海を知っているのかどうか気になりました。
突堤を挟んですぐ隣の埋め立て現場の海は、
今日は作業がなくて澄んでおり、大きなサンゴも透けて見えて、突堤から海中を泳ぐ魚の姿も見えたのに…
これからも、データを明示した記事をお願いいたします。
比較して見せてもらうことが、いちばん説得力を持つと思います。
わかりやすいご説明ありがとうございます。
今日、知人が東江の海を見に来てくれたのですが、
人工リーフを見て「魚のすみかを作ってるんでしょ?」と言いました。
護岸工事や養浜が今までの自然を変えてしまうのはわかるけど、また新しい自然が生まれないとも限らないでしょう、と。
60代のヤンバル生まれ育ちの方で自然を愛する気持ちも持っている方なのですが。
私は知識がなくて答えられませんでした。
この記事を紹介しようと思います。
今日は晴天で、東江の人工ビーチでシュノーケリングを楽しむ若者たちが居ました。
けっこう波が荒かったですが、人工リーフの上まで行っていました。
彼らが自然の海を知っているのかどうか気になりました。
突堤を挟んですぐ隣の埋め立て現場の海は、
今日は作業がなくて澄んでおり、大きなサンゴも透けて見えて、突堤から海中を泳ぐ魚の姿も見えたのに…
これからも、データを明示した記事をお願いいたします。
比較して見せてもらうことが、いちばん説得力を持つと思います。
Posted by 亜衣 at 2011年04月19日 02:39
亜衣 様
こんばんは。
釣り人の話しでは,人工リーフの水道部(外海へ通じる深みの部分)は,
場合によると離岸流(沖合に向かう強い流れ)が発生するときがあると
言っていました。普通の人なら沖に流されて驚き,
溺れてしまうかもしれません。
また,全国各地の突堤の先端でも似たような現象があり,水難事故が
多発しているそうです。
東江の人工海浜は防災上の施設であるため,人工ビーチではないようです。そのように設計されていないので,急に深くなったりしています。
これから夏に向かい泳ぐ人もたくさん出で来ると思いますが,
事故が起きないことを祈るばかりです。
私たちは,知らないことばかりです。
常に様々なことに関心を持ち,学んでいかなくてはなりませんね。
人工リーフのことも,調べてみて現実を知れば問題点が見えてきます。
続けていきましょう。
こんばんは。
釣り人の話しでは,人工リーフの水道部(外海へ通じる深みの部分)は,
場合によると離岸流(沖合に向かう強い流れ)が発生するときがあると
言っていました。普通の人なら沖に流されて驚き,
溺れてしまうかもしれません。
また,全国各地の突堤の先端でも似たような現象があり,水難事故が
多発しているそうです。
東江の人工海浜は防災上の施設であるため,人工ビーチではないようです。そのように設計されていないので,急に深くなったりしています。
これから夏に向かい泳ぐ人もたくさん出で来ると思いますが,
事故が起きないことを祈るばかりです。
私たちは,知らないことばかりです。
常に様々なことに関心を持ち,学んでいかなくてはなりませんね。
人工リーフのことも,調べてみて現実を知れば問題点が見えてきます。
続けていきましょう。
Posted by 有光智彦 at 2011年04月19日 03:05
at 2011年04月19日 03:05
 at 2011年04月19日 03:05
at 2011年04月19日 03:05